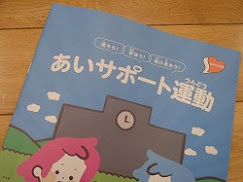明日からいよいよ7月。
で・・・
先週のある日・・・
午後の2年生の教室。
(じゃぁ~ん)
2年生がね・・・
「学級力会議」をしていたんです。
テーマは・・・
「7月から・・・
2年生ががんばるポイントはなんだろう?」。
1学期が・・・
のこり1か月をきっても・・・
" あ~あ もうすぐ夏休みだもんね。"とか・・・
" 暑いから・・・
ゆっくりでいいんじゃない?"なんてこと・・・
だれも思ってなんかいなかったんです。
まだまだ伸びようとしている・・・
みんなから出された意見は・・・
「くつそろえができていない」・・・
「ろうかを走っているひとがいる」・・・
「ひとのお話をきいていないひとがいる」・・・
そんなふうに・・・
しっかりと自分たちをみつめて・・・
しっかりと・・・
のこりの1か月をしめくくろうって・・・
みんなで話し合って・・・
7月にがんばるポイントを決めたんです。
やがてやってくる夏休みを・・・
充実した時間とするために・・・
そのあとおとずれる2学期を・・・
さらに成長する期間とするために・・・
" これでもか これでもか"って・・・
伸びようとする2年生のすがたを見ながら・・・
私は思っていたんです。
" ちっちゃかったきみたちって・・・
いつのまにか・・・
こんなにも大きくなっただけじゃあなくって・・・
こんなにもたのもしく・・・
こんなにもしっかりと・・・
考える力をつけたんだね。"って。
" みんな すごっ!"って。
" 2年生の「学級力会議」・・・
みんな すごっ!"・・・というお話でした。
実はこのとき・・・
もうひとつすごかったのはね・・・
(お・・・突然1年生・・・)
この学級力会議の様子を・・・
うしろでじいぃっと・・・
29人の1年生が・・・
固唾をのんで見つめていたことだったんです。
そのすがたはまるでね・・・
1年後の自分たちのすがたを・・・
みすえているようだったんです。
(すごっ!)